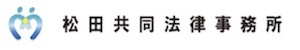保険・交通事故にいて(柔道)
第1 自賠責保険とは
1 自動車損害賠償保障法の制定の根拠
「走る凶器」たる自動車の普及交通事故の多発と被害者保護の必要性の増大
被害者保護ための措置
1 実質上の無過失責任
2 賠償能力の常時確保
ア 強制保険制度
イ ひき逃げ事故の政府保障
2 自賠責の支払い基準
傷害関係支払限度額120万円
1 積極損害
1 治療関係費
ア 入院費等
イ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、
きゅう師が行 う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
2 文書料
休業損害 1日原則として5700円
慰謝料 1日につき4200円
後遺障害関係
1 支払額
別表1の1(4000万円)から別表2の12級(224万円)、13級(139万円)、
14級(75万円)、死亡3000万円
2 損害額算定
ア 逸失利益 年間収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数、
イ 慰謝料等
別表1級 1600万円
別表2 12級(93万円)、13級(57万円)、14級(32万円)
傷害と後遺障害の区別
1 症状固定の意味
2 後遺障害の意味
ア 自動車事故による傷害がなおったとき(症状固定時)に残存する当該傷害と相
当因果関係のある障害
イ 将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態(障害の
永久残存性)
ウ その存在が医学的に認められ、
エ 労働能力の喪失を伴うもの
オ 自賠責施行令の等級に該当すること
第2 自賠責保険と任意保険の関係
1 任意保険
対人対物賠償保険 自動車事故による人身事故の被害者を救済するため、被保
険者が被害者に自賠法3条の損害賠償責任を負担することによって被る損害につき、
一定額を限度として填補する保険のこと
人身傷害補償保険 被保険者が、いわゆる人身傷害事故によって被った損害に
ついて、責任の確定や過失割合の決定を待たずに、保険契約(約款)上の損害額の
算定基準により算定された金額が支払われる保険
2 任意保険は、自賠責保険の上乗せ保険であること
3 一括処理加害者請求と被害者請求
3 柔道整復師がおこした事故例
1 交通事故の損害と認められる要件
I 医師の指示を要するかどうか
医師の指示を要するのを原則とする。
1 患者の健康状態に関し医学的見地から行う総合的判断は、医師しかできない。
2 医師による治療の必要性
柔道整復師は、レントゲン、MRI検査ができない。
3 客観的な施術効果の判定の困難性と限界
4 施術自体の多様性
5 施術の問題点
医師の指示がなくても施術が認められる場合
1 柔道整復師には法により許容されている業務範囲が存在すること
整形外科医により治療の代替機能を認められている。
2 外傷性のもので、発生原因が明確であることから、他疾患との関連が問題とな
ることは比較的少ないこと
3 施術の意義の存在
ア 施術は、痛みを和らげるのにある程度の効果があること
イ 施術内容と治療内容には共通部分があり、整形外科医による治療の代替機能があること
ウ 手技療法は、観血療法と比べて副作用及び人の身体に対する侵襲を伴わないものであること
エ 西洋医学的治療よりも効果的なケースが多々有ること
4 患者側の事情
ア 医療類似業は、整形外科より歴史が長く、地域に密着し、その効果についても
一定の評価を受けていること
イ 施術の利便性(かかり易さ)があり、医療機関よりも遅い時間まで受け付けており、
仕事が終わってからも施術がうけられ、また、施術所が近所にあるるため短時間で通え、
待ち時間も短いこと
ウ 施術はスキンシップが中心でりはり、親しみ易さが生まれ、
インフォームドコ ンセントに十分な時間がとれること
エ 患者は苦痛を早く取ってくれることを期待しているのであり、
医療機関の検査等の煩雑さもないこと
オ 患者には、注射、投薬などの副作用の危険と、
検査ばかりい追い立てる医療に対する不信があること
カ 患者の近くに医師がないという状況を考慮する必要があること
II 施術の有効性
痛みはこれを感じる患者の主観的体験であり、どの程度緩解すれば自制内と言え
るか判然としないが、施術により症状が緩解していることが立証することができれ
ば、治療効果が上がっていると認めて良い。
III 施術期間の相当性
(案)施術期間は、初療の日から6ヶ月を一応の目安とする。6ヶ月を超える場合
は、受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術効果等の観点から、施術の必要性が
立証できればこれを超える期間についての施術を認める。
痛みがあるという自覚症状のみで長期間施術を続けることを認め、加害者に施術
の全費用を負担させるのは相当でない。6ヶ月を経過した段階でも施術を受けなけ
れば鳴らない状態にある場合には、施術を含めて治療方法を見直す必要あがる。そ
のためには、6ヶ月を経過した段階で、整形外科医による診察を受け、種々の検査
を行って症状の原因を検討した上、医師の指示に従い改善策を検討すべきである。
施術に当たっては、治療効果を念頭におき、他の療法への切り替えを遅らせないことが重要である。
ただし、1受傷態様と施術部位の整合性に疑問がある場合、2私病あるいは既
往症が疑われる場合、3被害者が多様な症状を訴えている場合、4長期化が予想さ
れる場合、長期化の理由が明確でない場合、心因的要素が疑われる場合、5後遺障
害が予想される場合においては、その期間内であっても、医師の受診を要するもの
とする。
IV 施術費の相当性
モノおよび技術は、労災料金の1.5から2倍を上限の目安とする。なぜなら、
柔道整復師の施術は専ら徒手整復によるものであり、施術者によって施術の技術も
異なり、施術内容も多様であるから、施術者の技能の差がそのまま集客数と料金の
多寡に関連することになるし、交通事故の特殊性を考慮すると、労災料金を基礎と
しつつも、ある程度幅を持たせる必要があるからである。整形外科医においても、
過剰濃厚診療が行われた場合、社会保険上の診療報酬基準額の概ね2倍を超えた
場合は、その請求が制限されることとのバランス。
施術期間、料金、施術の必要性等の事情を斟酌して、施術費総額の何割の限度
で認める。
-5-